
猫の吐き戻しの原因とは?猫の病気や吐き戻し対策について紹介!
猫の吐き戻し頻度が高い理由

猫を飼っている人なら、猫が吐いている姿は度々見かける光景でしょう。
ここでは猫がよく吐いてしまう理由として考えられることをご紹介します。
早食いになってしまっている
猫の吐き戻し頻度が高い理由のひとつが、早食いです。
胃を圧迫する
猫は好きな食材やキャットフードを食べるとき、空腹のときには早食いになってしまうことがあります。
早食いをすることで空気を一緒に飲み込み、胃が圧迫されて吐き戻してしまうのです。
もともと野良猫だったり、多頭飼いなどで食事の取り合いになってしまう場合は、早食いになりやすく吐き戻しも多くなる傾向にあります。
また、ドライフードの場合は、胃の中で水分を吸い込んで急に膨らむことで、胃が圧迫されて嘔吐につながってしまうこともあります。
胃液や胆汁が逆流する
お腹がすきすぎているときや、胃の動きが低下しているときなどは胃液や胆汁が逆流してしまいます。
黄色い液体やフードを吐いてしまうときは、空腹が原因となっているケースが多いようです。
胃が驚く
空腹時に急にフードを食べることで、胃が驚いて吐き気をもよおします。
体内に毛玉が溜まっている
吐き戻しは毛玉が原因であることも少なくありません。
中でも換毛期でグルーミングの頻度が高いと、飲み込んだ毛玉が体内に溜まってしまい、吐き出す頻度が高くなります。
毛玉のほか、胃で消化できないものを飲み込んでしまったときや、胃袋よりも大きなものを食べてしまったときも吐き戻しにつながります。
▼猫の毛玉対策についての記事はこちら
病気によって吐いている
食べ物や毛玉以外にも、病気が吐く原因となっている場合があります。
考えられる病気としては、下記のようなものが挙げられます。
- 熱中症
- 寄生虫
- フードが原因で起こるアレルギーや中毒
- ウイルス性の伝染病
他にも悪性腫瘍によるものや、ストレスによる胃腸炎など消化器系のトラブルも嘔吐の原因になります。
何度も吐く場合は病気による可能性があるので、動物病院へ連れていくことをおすすめします。
猫が吐くもので体調確認

猫は吐き戻しが多いものですが、前述したように病気が隠れていることもあります。
病気かどうかを判断するためにも、何を吐いているかをチェックしてみましょう。
吐いたものが白い・黄色い場合
透明の液体や白い泡は『胃液』です。
黄色い液体の場合は『胆汁』である可能性が高いと言えます。
空腹の時間が長かったり、ひどくお腹が空いてるときは、胃液を吐くことがあります。
食事回数を増やす
白い液体や、黄色い液体を吐いてしまうときは、食事を何回かに分けて与えてみると良いでしょう。
食事をして元気になれば問題ありませんが、何度も嘔吐を繰り返す場合は病気の危険性があるので注意しましょう。
吐いたものが茶色い場合
ペースト状になった茶色いものを嘔吐した場合は、キャットフードを吐いたと考えられます。
消化しきれなかった場合は、固体に近いペースト状の嘔吐物をもどすことがあります。
病気の可能性もある
茶色い液体を吐いた場合は、消化器官や口の中が炎症を起こして出血し、血液が酸化して茶色くなってしまったことも考えられます。
また、嘔吐物が赤かったり、黒かったりする場合も出血によるものと考えられます。
重度の潰瘍や腫瘍の場合もあるので、早めに病院に連れていきましょう。
吐く頻度が高い場合はすぐ病院へ
嘔吐を繰り返す場合や、嘔吐したあと元気ない様子だったり、食欲もなかったりする場合は病気の可能性があります。
下痢なども起こしている場合は危険で、下記のような病気を起こしているリスクがあります。
- 胃炎
- 腸炎
- 腎不全
- 腸閉塞 など
腸閉塞などは放置しておくと命にかかわることもあります。
吐く頻度が高い場合には、すぐに診察を受け、適切な治療をしてもらいましょう。
毎日吐いてしまう場合

猫が吐いたものだけではなく、吐く頻度からも病気かどうか判断できる場合があります。
しかし、愛猫の頻度が高いのかわからない方もいるでしょう。
ここからは猫の吐く頻度について紹介していきます。
猫の吐く頻度
吐く回数が一日1~2回と少なく、下記のようなことが原因で、元気があれば問題はないでしょう。
- 食べ過ぎ
- 早食い
- 猫草など消化の悪いものを食べた
- 空腹
- 毛玉
しかし、繰り返し何度も吐いたり、毎日吐く場合は、病気や異物による嘔吐の可能性が高くなります。
また、何度も吐くことによって脱水してしまい、さらに危険な状態になってしまうこともあります。
症状の悪化を防ぐためにも、少しでも頻度が高いと感じたら病院へ連れていくことをおすすめします。
猫が吐けない場合
嘔吐したくてもできずにいたり、よだれが出ているときは、毛玉が溜まっているか異物を飲み込んで吐き出せない可能性があります。
放置しておくと消化器官に負担がかかるので、早めに病院に行きましょう。
猫は食道の唾液や粘液が少ない
猫はもともと食道の唾液や粘液が少ないので、フードが喉につかえたり、胃までいかずに食道内にひっかかってしまったりすることが少なくありません。
特に老猫になるとさらに粘液量が減り、フードを吐く頻度が高くなります。
吐き戻しできない猫への対策
猫が吐けない時の対策としては、フードに水分を含ませたり、水分量の多いフードに変えてみたりすることです。
また、早食いも喉に詰まるの原因になりやすいので、少しずつ分けてフードを与えるようにするとよいでしょう。
食事後しばらくしてから吐いた場合
食事をした後、時間が経ってからフードを吐いてしまう場合、消化器官の疾患のほか、内臓疾患の可能性もあります。
慢性疾患の場合は見た目に変化がわかりにくく、病気を進行させてしまうこともあります。
特に老猫は定期的に健康診断をすると安心です。
1日に何回も吐いたり、吐く回数が増えた場合は、できるだけ早めに病院で診てもらいましょう。
猫の吐き戻し対策

ここでは猫の早食いや、空腹による吐き戻しを減らすための対策について紹介していきます。
食事回数を増やす
前述しましたが、早食いが嘔吐につながっているときの対策として効果的なのは、食事の回数を増やすことです。
空腹の時間を減らせば、早食いを防ぐことができるでしょう。
1度に与える量を減らし、食べ過ぎないようにすることも大切です。
食事回数を増やすと空腹を感じにくくなりますが、それでもごはんを要求する場合には、おやつを与えるのもおすすめです。
猫がゆっくり食べられる環境を作る
複数の猫を飼っている場合は、食事の場所を別にして猫がゆっくり食べることができる環境を作りましょう。
他の猫に取られる心配がなければ、早食いをしなくなるかもしれません。
キャットフードを変える
キャットフードの粒を大きいものに替えてみるのもおすすめです。
しっかり噛まなければ飲み込めないので早食い対策になります。
ただし、粒が大きすぎると、猫によってはそのまま飲み込んでしまうことがあります。
また、フードの形がとがっていると喉に引っかかったり、喉が刺激されたりして嘔吐につながることがあります。
お皿を変えてみる
早食いや大食い対策として食事用のお皿を変えてみるのも一つの方法です。
凹凸のあるお皿などでフードを与えれば、お皿の側面や底などの突起が邪魔をして一気に食べられないので、早食い予防になります。
ゆっくり食べることで喉へのつまりや胃腸への負担を軽減し、吐き戻しを防げるでしょう。
よく吐いてしまう場合のキャットフード

食べてすぐ吐く場合、キャットフードが合っていない可能性があります。
キャットフードが吐く原因となる理由
キャットフードの粒が大きすぎれば、喉につかえてしまうこともあり、小さすぎれば食べ過ぎてしまうこともあります。
フードの形や素材が喉に負担をかけていることで、嘔吐につながることもあります。
または、猫の口に合わずに吐いてしまうということも考えられます。
現在使用しているフードを違うものにして、様子を見てみましょう。
医師に従ってフードを選ぶ
フードの素材や添加物などが原因で、アレルギー反応を起こしていることもあります。
特定のものを食べて吐いたり、毛づやが悪かったりするときはアレルギーの可能性もあるので、動物病院で医師の指導に従ってフードを選ぶようにしましょう。
吐き戻し軽減フード
吐き戻し軽減フードを与えるのも対策の一つです。
吐き戻し軽減フードはお腹の中で粒が素早くふやけ、胃の圧迫を防止できるようになっています。
また、水分を素早く吸収し胃の中での消化をサポートしたりする機能によって、吐き戻しの軽減が期待できます。
独自の食物繊維を配合し、体内の毛玉の排出をサポートする効果が高いものもあります。
効果がないこともある
吐き戻しの原因は様々あるので、フードを替えただけでは嘔吐が軽減されないこともあります。
フードを変えても頻繁に吐いてしまう場合には、一度動物病院で診察してもらいましょう。
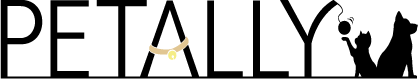









_s-200x200.jpg)











